「調剤薬局で働きたいけれど、どんな仕事内容なのかな?」
「調剤薬局と言えば調剤メインなイメージだけど…他の仕事は?」
という疑問の声は、薬局に転職・就職したい薬剤師の方に多く聞かれます。
医薬分業元年と言われる1974年以降、医薬分業の流れが進み、調剤薬局は院外調剤を応需する場所というイメージでとらえられることが多くなっていました。
しかし実際には、調剤薬局は調剤以外にも様々な業務を行っています。近年は地域包括ケア推進の流れを受けて、薬局が在宅医療に関わる場面も増えてきました。
今回は調剤薬局で働く薬剤師の仕事内容や求められるスキル、近年の調剤薬局を取り巻く状況などをお伝えします。この記事を読むことで、調剤薬局で働く具体的なイメージができ、迷わず転職・就職活動を行えるようになります。
調剤薬局で働く薬剤師の仕事内容
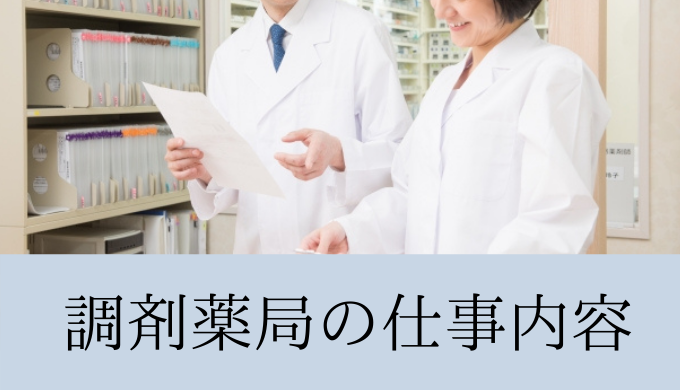
調剤薬局で働く薬剤師の主な仕事は、医師の処方せんによる調剤業務ですが、他にも様々な業務を行っています。ここでは具体的な業務内容をお伝えします。
調剤
調剤は、医師が発行した処方せんに書かれている薬を準備する業務です。ただ薬を取りそろえるだけでなく、「処方監査」として医師の処方内容(用法・用量・日数など)に問題が無いか確認を行い、必要時には疑義紹介を行います。
併用薬との飲み合わせや患者の病歴・アレルギー歴などから、処方内容を総合的に判断します。
服薬指導
調剤した薬を患者に交付し、薬の用法用量や注意点などを説明する「服薬指導」も、薬剤師の重要な業務です。
政府主導で薬局の対人業務が推進されており、服薬指導は薬剤師の重要業務と位置づけられています。
見本を用いて吸入薬や点鼻薬などの使い方を説明したり、小さな子供でも無理なく飲める服用方法を提案したり、患者の状態や理解力に合わせた指導を行います。
薬局内だけでなく、自宅に帰った後も継続的なフォローアップが必要とされています。
2020年9月に施行された改正薬機法では、薬剤師に対し「調剤した薬剤の適正な使用のために、必要な場合は患者の使用状況を継続的・的確に把握して、患者や家族などに必要な情報を提供し、指導を行わなければならない」と明記されています。
副作用や飲み間違いの恐れがある場合など、継続的な指導が必要と判断されるケースでは、電話や訪問などでの確認をするよう求められているのです。
薬歴管理
薬歴管理とは、服薬指導で得た情報を、薬剤服用歴管理簿(以下、薬歴)に記載して管理する業務です。症状経過や既往歴、副作用歴などを聞き取って薬歴に記入し、他の薬剤師と情報共有できるようにしています。
薬歴は「薬剤服用歴管理指導料」の算定要件でもあり、最終記載日から3年間は保管しなければなりません。
在宅業務
在宅業務では自宅療養している患者の自宅を訪問し、服薬指導・薬の管理指導などを行います。
地域全体で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」が推進される中で、調剤薬局に地域密着型の機能が求められるようになり、実際に多くの調剤薬局が在宅業務に進出しています。今後ますます、薬剤師の活躍が求められていくでしょう。
医療機関との連携
患者に適切な医療を提供するには、薬局内の業務にとどまらず、医療機関と連携していく必要があります。患者が医師に伝えそびれていた症状や副作用、残薬状況などを聞き取った際には、処方元の医師に適切にフィードバックしなければなりません。
令和3年8月1日から認定が始まった「地域連携薬局」では、患者に対して他職種との連携を図りながら、薬局が地域包括ケアシステムの一翼を担うことが求められています。
地域連携薬局の認定要件の一つとして、地域の医療機関に月平均30回以上、入退院や居宅訪問などに関する情報共有を行った実績が必要とされています。
健康相談・セルフメディケーション増進
調剤薬局の薬剤師の仕事には、処方せん関連の業務だけではなく、地域住民からの健康相談・介護相談も含まれます。
健康相談を受けて病院への受診勧奨を行ったり、OTC、サプリメントなどでのセルフメディケーションの支援を行ったりすることも大切な薬剤師業務です。
厚生労働省は「健康サポート薬局」認定制度を設け、疾病前の未病の段階から健康相談などにより地域住民の健康の維持・増進をサポートできるよう、薬局の機能向上を推進しています。
薬局は保険調剤だけを収益源とするのではなく、健康サポートや在宅医療、地域連携への進出を求められているのです。
その他(受付・医薬品在庫管理など)
「処方箋受付」や「医薬品の発注業務」は調剤事務が行うケースも多いのですが、調剤事務の不在時には薬剤師が行う必要があります。
受付業務は来局患者から処方せんやお薬手帳を受け取り、必要に応じて保険証を確認も行います。
その後、レセプト(調剤報酬明細書)を作成するためにレセコン(レセプトコンピューター)に処方せんの内容を入力しますが、調剤事務の不在時にはやはり薬剤師が入力を行わなければなりません。
薬剤師は、医薬品の在庫管理も担当しています。調剤事務が発注をする場合もありますが、薬剤師が行うケースもあるでしょう。
医薬品が納品されたら、注文内容と合っているか検品を行い、問題なければ入庫します。これらの業務も必要に応じて薬剤師が行っています。
調剤薬局で働く薬剤師の年収
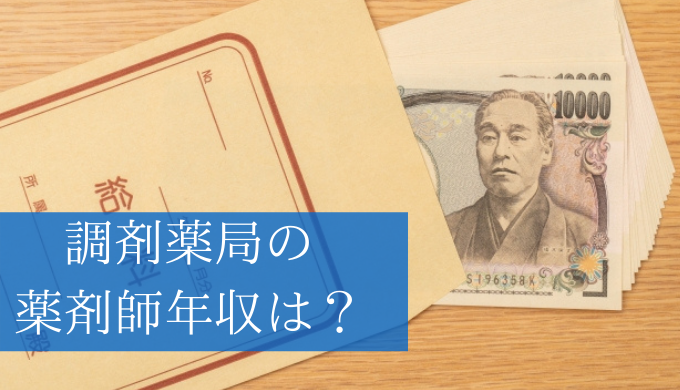
調剤薬局で働く薬剤師の年収は、一般的には病院より高く、ドラッグストア・製薬企業よりも低いことが知られています。
マイナビ薬剤師が保有している求人から業種別の平均年収によると、
業種 平均年収 病院薬剤師 434.6万円 調剤薬局 488.3万円 ドラッグストア 512.5万円 製薬会社 543.2万円
このように、調剤薬局の年収は中程度の水準であることが見て取れます。
ただし、年収は薬局の規模や勤務地域、経験年数や役職により大きく異なるため、単純に平均値だけを比較しないように注意しましょう。
地方では薬剤師の人数不足などの背景から都市部より年収水準が高く、また、小規模な調剤薬局は人材を確保するために高年収を提示しているケースが多いです。
調剤薬局の薬剤師の勤務時間・残業
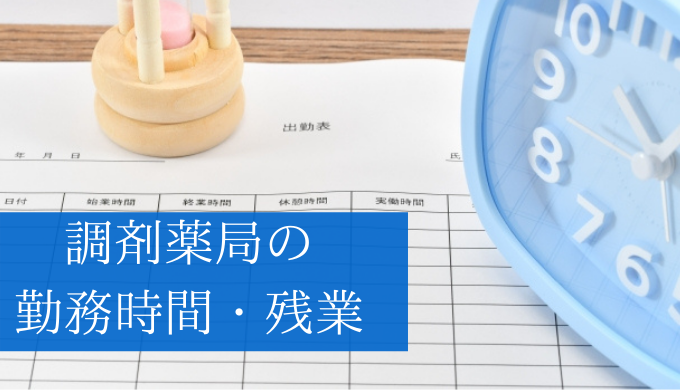
調剤薬局の営業時間は9時〜18時前後に設定されているケースが一般的で、周辺クリニック等の診療時間に合わせている薬局が多いです。
例えば、土曜日を診療日に設定しているクリニックの門前薬局では、そちらのクリニックにならって平日1日+日曜日を定休日にしている場合があります。
また、来局患者が増える冬場の風邪流行期や花粉症シーズンでは、処方せんの応需枚数が増えて残業が多くなる傾向があります。
調剤薬局の薬剤師として働くメリット・デメリット
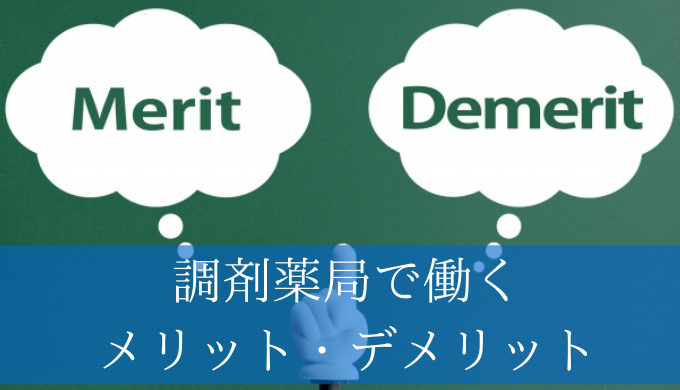
調剤薬局で働くメリット・デメリットをご紹介します。
調剤薬局で働くメリット
調剤薬局のメリットは、患者に直接触れ合えることから仕事のやりがいを得やすいことです。
また、ドラッグストアに比べて営業時間が短めであり、日曜と祝日を休みとするケースが多いため、比較的休みやすいのもメリットと言えるでしょう。パート・アルバイトでも2000円を越える高額の時給を得られるため、家庭環境やライフスタイルに合わせて柔軟な働き方が可能です。
調剤薬局で働くデメリット
調剤薬局のデメリットとしては、狭い空間で同じスタッフが密になって働いているため、人間関係が閉鎖的になりがちなことが挙げられます。
調剤室の面積は比較的狭いため、長時間一緒に仕事をしている上司や同僚との相性が悪いと、十分な距離を取れずに働きづらさを感じる人もいます。
実際に、人間関係を理由に転職する薬剤師は非常に多いです。密な労働環境を苦痛に感じず、周りに振り回されずにコミュニケーションを保てる人であれば、あまり問題にならないでしょう。
また、閉鎖的な環境下では一般的なビジネスマナーが身につけづらいというデメリットもあります。マナー研修を設けられている薬局を選ぶか、自身で意図的に学習することでビジネスマナーを身につけることが可能です。
調剤薬局の薬剤師に必要なスキル

調剤薬局の薬剤師には、自己研鑽をして専門知識を高めていく意欲や、患者・他スタッフとのコミュニケーション能力、在宅医療への知識と技能などが求められます。
専門知識
薬剤師の国家資格は更新のない資格ですが、薬剤師として働くためには医薬品や関連法規の情報は日々をアップデートして専門知識を高めていく必要があります。
「かかりつけ薬剤師」の算定要件にも研修認定薬剤師の取得が含まれており、薬剤師の自己研鑽が欠かせません。
また、令和元年12月の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」を受け、令和3年8月から地域連携薬局と専門医療機関連携薬局の認定制度が開始されました。
いずれの認定を受ける場合にも、薬剤師としての専門知識やスキルが求められます。
- 地域連携薬局
:外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報連携に対応できる薬局 - 専門医療機関連携薬局
:がん等の専門的な薬学管理が必要な利用者に対して、他の医療提供施設との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局
コミュニケーション能力
調剤薬局は従来の調剤中心の対物業務から、患者と関わる対人業務への変換が求められています。それに伴い、コミュニケーション能力の向上が重視されています。
- 患者とのコミュニケーション
:服薬状況の聞き取り、副作用の聴取、情報提供 - 医療関係の他職種とのコミュニケーション
:地域医療連携による医療情報の提供・共有
調剤薬局の薬剤師は地域包括ケアシステムの構成要因として、患者や医療関係者とのコミュニケーション能力を高めていく必要があります。
在宅医療のスキル
超高齢化社会を背景に在宅医療の需要が高まっているため、在宅医療・地域医療のスキルの向上が必須です。
具体的には、服薬状況を一元的・継続的に管理して指導を行ったり、多剤・重複投薬を防止したり、残薬解消などにより医療費の適正化に導いたりするための技術や知識が求められています。
調剤薬局の薬剤師を取り巻く近年の動向
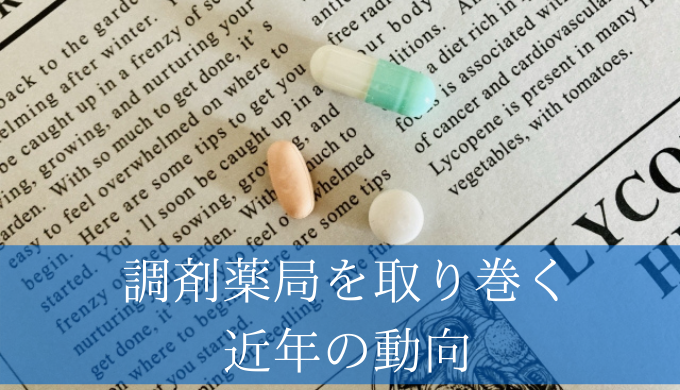
日本は世界でも類を見ない超高齢化社会に突入しており、調剤薬局に求められる役割も日々変化し続けています。調剤薬局を取り巻く近年の動向を解説します。
かかりつけ薬剤師制度
2016年にかかりつけ薬剤師制度が新設され、薬に関していつでも気軽に相談できる環境を整備することが調剤薬局の役割として求められています。
「かかりつけ薬剤師」の役割は、薬・健康・介護に関することなどに豊富な知識と経験を持ち、患者さまの相談に応じたり健康管理をサポートしたりすることです。
医療の高度化や細分化により1人の患者が複数の医療機関を受診する機会が増えており、服薬管理や過剰残薬に悩む患者も少なくありません。かかりつけ薬剤師の活躍が期待されています。
調剤事務・調剤補助員の業務拡大
2019年4月2日の厚生労働省からの通知、いわゆる「0402通知」を受けて、非薬剤師の業務拡大の流れにも留意する必要があります。
薬剤師の責任・監督下であれば、一部の調剤などを薬剤師資格のない人が行っても問題ないことが示され、薬剤師の代わりに調剤事務・調剤補助員が一部調剤を行うようになってきました。
1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること。
・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがない こと
・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
今後ますます薬剤師の調剤業務に関わる負担は軽減され、対人業務にかける時間が増えていくことは間違いないでしょう。
調剤薬局への転職を成功させるには転職サイトの活用を

まだまだ全国的に薬剤師不足が不足している調剤薬局は多く、調剤薬局の薬剤師の求人情報を見つけるには比較的容易です。しかし、自分の希望に合った薬局をしっかりと選ぶためには、就職先をきちんと吟味しなければなりません。
転職してから「こんなはずではなかった…」と後悔しないためにも、転職サイトに登録して情報収集することを強くおすすめします。
薬剤師に特化した専門求人サイトでは、担当エージェントが希望条件をきちんとヒアリングした上で、あなたの理想に適った求人を複数紹介してくれます。
実際に見学したり、エージェントを通して給与や待遇の条件交渉をしたりすることで、失敗のない転職を叶えられるでしょう。
まとめ
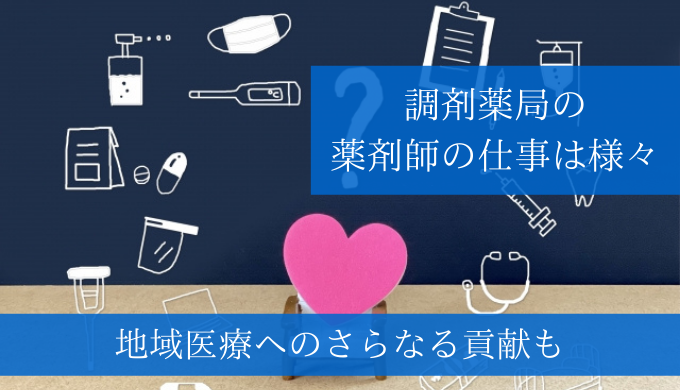
- 調剤薬局の薬剤師は調剤だけでなく患者の安全な服薬に関する様々な業務を行っている
- 地域包括ケア推進により、薬局薬剤師の在宅医療への進出が求められている
- 自分に合った調剤薬局を正しく選ぶためには、転職サイトを利用して十分な方法収集を行うとよい
以上、薬局薬剤師の仕事内容や近年の動向などについてお伝えしました。
薬局薬剤師の仕事は地域医療に貢献でき、今後ますます重要度が高まっていく職業と言えるでしょう。
就職先の情報収集を入念に行い、理想の転職を叶えてくださいね。





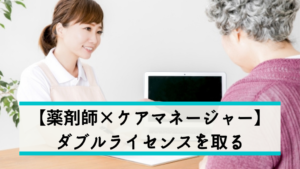
コメント