「薬剤師にはどんな就職先がある?」
「薬局以外で薬剤師免許は活かせない?」
薬剤師の就職先の定番といえば、調剤薬局や病院などをイメージされる方も多いのではないでしょうか?
しかし、薬剤師の活躍の場は薬局だけではありません。
薬剤師にはさまざまな就職先があり、その業務や職種は多岐にわたります。
そこで、この記事では薬剤師の就職先と給与や仕事内容まで、さまざまな視点から薬剤師の進路を解説しています。
就職先に迷っている薬剤師や薬学生は必見です!
本記事で分かること
- 薬学生の卒業後の進路
- 学歴別・偏差値別の進路
- 薬剤師の就職先ごとのメリットデメリット
- 就職先ごとの年収を比較
- 就職先を選ぶ際のポイント
薬学生の卒業後の進路
まずは、薬剤師を目指している薬学生がどのような就職先を選んでいるのかみていきましょう。
以下では、薬学生の卒業後の進路について解説しています。
卒業生の約6割が薬局に就職
参考:厚生労働省 平成 30(2018)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況
厚生労働省の調査によると、6年制薬学部卒業後の就職先のトップは調剤薬局(ドラッグストアを含む)でした。
その次に、病院や老人ホームなどの医療福祉施設、製薬会社、行政機関、大学の順となっています。
つまり、卒業生の約6割が薬局に就職しているのです。その理由として、薬剤師の男女比が関係しているとされています。
薬剤師の男女比は男性38.7%、女性が63.3%の4:6です。
つまり薬剤師は、圧倒的に女性が多い職業のため結婚や出産のライフスタイルに合わせた働き方ができる調剤薬局が就職先として人気。
薬剤師の就職先は幅広い
上記のように、薬剤師の就職先で多いのはドラッグストアを含む調剤薬局ですが、薬局だけが薬剤師の就職先ではありません。
薬剤師の就職先は幅広く、以下のような職場があります。
薬剤師の就職先
- 製薬会社
- 化粧品会社
- 健康食品会社
- 保健所
- 厚生労働省(麻薬取締官)
- 大学の研究室
- 開発・研究所
- 学校
このように薬剤師は、身近な企業や施設にも多くの就職先があるのです。
主に薬剤師が必要とされる場面は「医学・薬学」の知識。
こうした知識を活かせるのは単に、医療現場や薬局だけでなく、さまざまな場所で活躍が期待されています。
「就職しない」という選択肢も
薬学生の進路は、就職することだけではありません。
6年制の薬学部を卒業した後、さらに大学院の博士課程に進学するという選択もあります。
薬学部の大学院を卒業するには、さらに4年の歳月がかかるといわれているのです。
また、海外の薬学部に留学しその国の薬剤師免許を取得するという道もあります。
このように、薬学部卒業後は目標や夢を叶えるためにあえて「就職しない」という選択をする人もいるでしょう。
薬剤師の就職先に学歴(偏差値)は関係あるのか
薬剤師の就職先には学歴による影響はあるのでしょうか?
以下では、薬学生の就活時における学歴の関係について調査しました。
就職活動では一つの指標となる偏差値
就職活動では、どこの大学を卒業するかによって就職先が、異なってきます。
まずは、偏差値別に2つの大学の就職状況を見ていきましょう。
以下は、偏差値50〜57の東京薬科大学の就職先を男女別にまとめたものです。
| 東京薬科大学 薬学部 偏差値(50〜57)就職状況 | ||||||
| 就職先 | 企業 | 調剤薬局 | ドラッグ ストア | 病院 | 公務員 | 進学 |
| 男 | 20.8% | 24.9% | 28.9% | 12.7% | 3.5% | 5.8% |
| 女 | 17.2% | 33.0% | 20.8% | 25.8% | 0.5% | 0.5% |
参考:東京薬科大学年度別進路状況より
上記の表を見てみると、男性はドラッグストア、女性は調剤薬局が最も多い就職先です。
ドラッグストアは給与は良いですが、残業や休日が少ないため、女性は残業が少ない調剤薬局に人気が集中しました。
また、男性の進学率も高く大学院にいく薬学生も多いようです。
ちなみに、東京大学薬学部の学生の9割は就職せずに、大学院へと進学するというデータもありました。
次に、偏差値49の奥羽大学の就職先状況を見ていきましょう。
| 奥羽大学 薬学部(偏差値49)就職状況 | ||||||
| 就職先 | 企業 | 調剤薬局 | ドラッグ ストア | 病院 | 公務員 | 就職準備者 |
| 男 | 0% | 12% | 44% | 24% | 1% | 19% |
| 女 | 0% | 40% | 16% | 28% | 0% | 16% |
こちらの表を見ていくと、男性がドラッグストアと女性が調剤薬局が就職先として最も多く、この辺の傾向は東京薬科大学と変わりません。
しかし、奥羽大学は病院に就職する学生が多いということが分かりました。
また、卒業後も就職先が決まらない学生も一定数いるようなので、偏差値が低い大学では就職活動が難航していることが分かります。
このように、大学の特色や偏差値によって薬学生の就職先はかなり異なっているのです。
そのため、薬剤師になるための大学選びでは、卒業生がどのような就職先で働いているのかを知ることも大切だといえるでしょう。
就職してしまえば学歴は関係ない
ここまでで、大学の偏差値で就職先が変わることをお伝えしてきました。
しかし、一度就職して働いてしまえば薬剤師の場合、免許さえ取得していれば学歴は関係ありません。
なぜなら出身大学が違っても同じ企業で働いていれば、薬剤師自体の業務や給与には大差がないからです。
そのため、就職活動の時だけある程度学歴や偏差値で比較されたりしますが、内定し入社してしまえば学歴は関係ないといえるでしょう。
薬剤師の就職先ごとにメリットデメリットを解説
薬剤師の就職先には、薬局だけでなく公務員や製薬会社などさまざまな職場があります。
そこでこの項目では、薬剤師が活躍できる7つの就職先のメリットデメリットについて解説していきましょう。
メリットデメリットを知ることで、自分に合った就職先が分析できるはずなのでぜひ参考にして下さい。
調剤薬局で働くメリットデメリット
薬剤師の最も多い就職先が調剤薬局です。
勤務地の多さや残業の少なさから、女性に人気の就職先で選択肢も豊富。
そんな調剤薬局で働くメリットデメリットを見ていきましょう。
調剤薬局は、営業時間や休みが不規則ではないので、プライベートが充実させやすい傾向にあります。
また、調剤のスキルや患者さんと直接コミュニケーションがとれるので、薬剤師としてのキャリアが積みやすいのが特徴です。
管理薬剤師のポストになれば、高年収を狙えるのも魅力だといえるでしょう。
調剤薬局は、女性が多い職場のため人間関係で悩むことも少なくありません。
また、普段は同じ薬剤師同士での交流が多いため情報が偏りがちです。
クリニックや病院にに併設している調剤薬局では、処方内容が偏りがちでワンパターンになる傾向にあります。
個人経営や中小薬局だと経営者の裁量が介入しやすく、独特な細かいルールがあるので働きづらくなってしまうというデメリットがあるのです。
ドラッグストアで働くメリットデメリット
ドラッグストアは、調剤薬局の次に人気がある就職先で、需要も高い職種です。
以下では、ドラッグストアで働くメリットデメリットを見ていきましょう。
ドラッグストアのメリットは、新卒で入社しても他の就職先よりも年収が高い傾向にあります。
大手企業によっては、新卒でも年収500万円以上で募集している企業もあるようです。
また、ドラッグストアの魅力はOTC医薬品を多く扱っているので、OTCに関する知識が身につきます。
将来的に独立を考えている薬剤師は、ドラッグストアでマーケテイングや経営スキルが身につくでしょう。
最近では、調剤薬局併設型のドラッグストアも増えていて、さまざまな処方箋が扱えるようになったのも魅力です。
ドラッグストアでは、24時間営業の店舗も多く人手不足から残業を余儀なくされることも多いようです。
また、レジ打ちや商品陳列など薬剤師以外の業務も多く、やりがいを感じられなくなってしまうことも。
OTC医薬品しか扱っていないドラッグストアでは、調剤経験ができないというデメリットもあります。
病院で働くメリットデメリット
病院で働く薬剤師は、入院患者や外来患者の治療行為を行う「臨床医学」の現場として活躍できます。
医師や看護師などのチーム医療の一員としての役割を果たす、病院薬剤師のメリットデメリットを見ていきましょう。
病院薬剤師は、他の医療従事者と身近に接する機会が多いため、さまざまな視点から物事を考えることができます。
また、調剤薬局では扱えないような薬剤師を扱うこともあり、経験が豊富になることも魅力です。
入院している患者さんを間近で経過観察できるのも、病院薬剤師のメリットだといえるでしょう。
病院薬剤師のデメリットは、夜勤や救急外来に対応できる人材が求められます。
そのため、勤務時間が不規則になりやすいのがデメリットです。
また、さまざまな医療従事者と連携して仕事を進めなければいけないので、高いコミュニケーション能力がないと勤務は難しいでしょう。
病院薬剤医師は、年収相場が低めに設定されているのもデメリットです。
企業で働くメリットデメリット
薬剤師の中には、薬学知識を活かして企業で働くという選択肢があります。
例えば、食品メーカーや化粧品メーカーの研究員として実験や開発業務を担当し、企業に貢献していくのです。
以下では、薬剤師が企業で働くメリットを見ていきましょう。
一般企業は、土日休みのところが多く福利厚生も充実しているメリットがあります。
また、臨床試験や開発で自社製品が、製造されていくやりがいは他の薬剤師には経験できない達成感があるでしょう。
また、社内では「薬学の専門家」として信頼のおける存在として働くことができるのです。
大企業の場合、転勤や異動は会社員の宿命といってもいいでしょう。
また、研究や開発職として採用されると患者との関わりがなく、薬剤師らしい業務はありません。
企業の業績や経営状況によっても、賞与や給与が変動するのも、デメリットです。
MRとして働くメリットデメリット
MR(医療情報提供者)は、医師や医療従事者に対して正しい医薬品の知識を伝達する重要な役割を担っています。
MRは、薬剤師以外でも働くことができる職種ですが、薬剤師資格を持っているMRであれば薬学知識を活かした情報提供が可能です。
そのため、医療従事者から信頼を得やすいのも薬剤師MRのメリットだといえるでしょう。
その他のMRのメリットデメリットは、以下のようなものがあげられます。
MRの仕事は、自社製品の医薬品を使用してもらうために、効能や副作用を正しく伝え売り込んでいきます。
そのため、大口契約がいくつもとれることで収入が上がり、高年収が期待できるのです。
また、社会人に欠かせないビジネスマナーやプレゼン力が身につくこともメリットだといえるでしょう。
MRの魅力は、高年収ですがインセンティブ要素が大きく結果が伴わないと高給になりません。
また、遠方への出張や転勤、休みの日も接待など忙しいものMRの特徴です。
そのためMRは、結果が求められるシビアな業界だといえるでしょう。
公務員として働くメリットデメリット
公務員薬剤師といってもその職場は幅広く、さまざまな職場があります。
地域の衛生環境を守る地域に密着した保健所から、国の研究機関や国立病院など活躍の場は細かく分けられます。
公務員薬剤師のメリットデメリットは以下の通りです。
公務員のメリットは、なんといっても収入と雇用の安定さです。
世の中が不景気な状況でも公務員は、安定した収入が得られます。
また、リストラの心配もありません。
地域住民や国民の生活を豊かにするために、公務員薬剤師は欠かせない存在です。
そのため、やりがいや使命感は大きいでしょう。
残業が少ない点や福利厚生が充実しているのも、公務員薬剤師のメリットです。
公務員薬剤師のデメリットは、はじめのうちは給与が低い傾向にいあります。
しかし、年齢や勤続年数に比例して順調に給与は上がっていくので、給与の低さで不安になるのははじめだけです。
また、公務員は業務に支障が出ることを避けるため、副業が禁止されていますので、注意しなければなりません。
公務員という、会社員とは違うキャリアを歩むため薬剤師としての調剤経験や服薬指導などのスキルは身に付きにくい職種だといえるでしょう。
大学で働くメリットデメリット
薬剤師の就職先として大学職員になる進路があります。
自分が在学していた大学で研究を継続したり、教授の補佐として働きながら生徒に教えていく仕事内容です。
以下では、大学で働くメリットデメリットを解説していきましょう。
大学で働くメリットは、自分が学んできた知識を生徒に教えたりできるやりがいがあることです。
また、研究設備が整っているので、さまざまな実験が行えます。
生徒から刺激をもらえることもある職業であり、大学で働く意味は非常に大きいといえるでしょう。
大学で働くデメリットとしては、給与が低い傾向にあり、調剤経験が身に付かないところがあります。
また、決まった人間関係でしか仕事ができないため、どうしても閉鎖的な職場になりがちになるでしょう。
大学生の延長のような気分で働いていると、いつまでたってもスキルが身に付かないことになるので、積極的な提案や研究姿勢が求められる職種です。
薬剤師の就職先の年収を比較
薬剤師として就職するなら誰もが給与がいいところで働きたいと思うのは当然です。
そこで、就職先ごとの平均年収を解説していきましょう。
以下の表は、薬剤師の就職先ごとの初任給と平均年収をまとめました。
| 職場 | ドラッグストア | 病院 | 調剤薬局 | 企業 | MR | 公務員 |
| 平均初任給 | 約30万円前後 | 約20万円前後 | 約25万円前後 | 約23万円前後 | 約22万円前後 | 約20万円前後 |
| 平均年収 | 約400万〜約700万円 | 約300万〜約550万円 | 約400万〜約650万円 | 約450万〜約750万円 | 約500万〜約800万円 | 約400万〜約700万円 |
参考:厚生労働省 賃金構造基本統計調査
薬剤師の就職先で最も初任給が高いのが、ドラッグストアです。
しかし、下の平均年収を見てみるとドラッグストアの年収は、そこまで高くなく初任給からの給与はあまり伸びていない傾向があります。
最も給与が上がりやすい薬剤師の就職先は、MRや公務員です。
MRは、業績次第で給与が上がるシステムなので、頑張り次第では年収1000万円も夢ではありません。
また、公務員は初任給が低いですが、最終的に昇給率が最も良い就職先です。
この表はあくまでも平均的な年収なので、企業によっては上記の給与を下回ったり、上回る場合があります。
就職先の参考程度にしていただければ幸いです。
新卒の薬剤師が就職先を選ぶ際のポイント

新卒の薬剤師が就職先を選ぶ基準は給与も重要ですが、それだけで決めてしまうと職種のミスマッチが起こります。
就職のミスマッチを避けるには、どのように選ぶのが最適なのでしょうか?
以下では、薬剤師の就職先選びのポイントを解説していきましょう。
自己分析をしっかりと行う
就職先選びで失敗しないためには、自己分析が重要な鍵を握っているといっても過言であはりません。
自己分析をしっかりと行うことで、自分に向いている職種や適正が分かるでしょう。
また、自分の理想とするライフスタイルや就職する上で譲れない条件を明確にすることで、効率良く応募先を決めることができます。
自己分析を行うには、過去の体験やアルバイト、自分の強みや弱みなどから知る必要があるでしょう。
また、インターネット常にある自己分析診断や適正検査をやってみるのもおすすめです。
自分の傾向や適正を知ることで、スムーズな就職活動ができます。
希望する業界事情を知る
自己分析が十分にできたら、希望する業界について調べてみましょう。
自分が希望している業界事情を知ることにより、新たな発見や働く前のミスマッチを防げます。
業界事情を知るには、ニュースや新聞、専門誌をくまなくチェックし情報を収集するのがおすすめです。
業界の将来性や傾向を知り、将来自分がどのようになりたいのかを明確にしておきましょう。
OB・OGの生の声を聞く
就職活動中には、さまざまな就職先の先輩薬剤師から話を聞く機会が多くあります。
しかし、実際に働いてる本音や仕事の大変さなどは、聞きづらい傾向にあるでしょう。
そこで、大学を一足早く卒業して薬剤師になったOB・OGを訪問し、実際の仕事内容や生活を見聞きすることで企業の本来の姿が分かるのです。
学会に参加する
企業での研究職や大学への就職を希望している人は、学会に参加しましょう。
学会に積極的に参加することで、別の研究室や大学とのつながりができ、就職先の幅が広がります。
また学会によっては、就職に関する見学会や相談コーナーもあるので、活用するのがおすすめです。
大企業だけでなく中小企業にも目を向ける
就職活動をしていると、真っ先に思い浮かぶのが大企業ですが、競争率が高く選考にも時間がかかる傾向にあります。
確かに、大手企業の方が給与や待遇面でメリットは多いでしょう。
しかし、中小企業や地域に密着した企業にも、給与や福利厚生などが充実している会社はたくさんあります。
大企業だけでなく、中小企業にも目を向けて就職活動を進めることで、自分に合った企業を見つけやすくしてくれるのです。
新卒薬剤師の就職先は将来のキャリアにも影響する
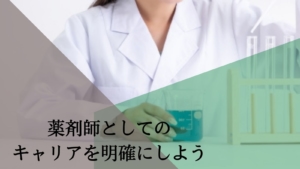
新卒で、どの就職先で働くかは薬剤師にとしてのキャリア形成の第一歩です。
そのため最初の就職先は非常に重要で、自分が働くことへの価値観を見出す場所になります。
高いモチベーションで働くことで、出世のチャンスやキャリアアップのスピードが期待できるのです。
しかし、十分な自己分析や情報収集を行なっても、実際に働いてみないと分からないことも多いでしょう。
そこで、おすすめなのが薬剤師専門の転職エージェント。
転職エージェントは転職者のためのサービスだと思われがちですが、新卒でも登録し活用できます。
コンサルタントと呼ばれる担当者が一人ひとりに付き、就職先に関する相談やあなたにあった求人を紹介してくれるのです。
このようなサービスを活用することも、就職活動を賢く進めるポイントでもあります。
おすすめの薬剤師転職サイトについては、下記の記事をご覧ください。
まとめ:薬剤師の就職先は幅広い
ここまで、薬剤師の就職先について解説してきました。
薬剤師の就職先は、薬局だけにとどまらずさまざまな活躍の場があります。
まとめ
- 薬剤師の就職先の約6割が調剤薬局へ就職する
- 就職先は偏差値や大学の企業との繋がりが影響してくる
- 就職活動で大切なのは自己分析と情報収集
- 就職先はキャリア形成への第一歩
理想の就職先を見つけるためには、業界の将来性や自分がどんな薬剤師になりたいのかをしっかりと固めていくことが大切です。
ぜひ、本記事を参考に後悔のない就職先を見つけてみてはいかがでしょうか?
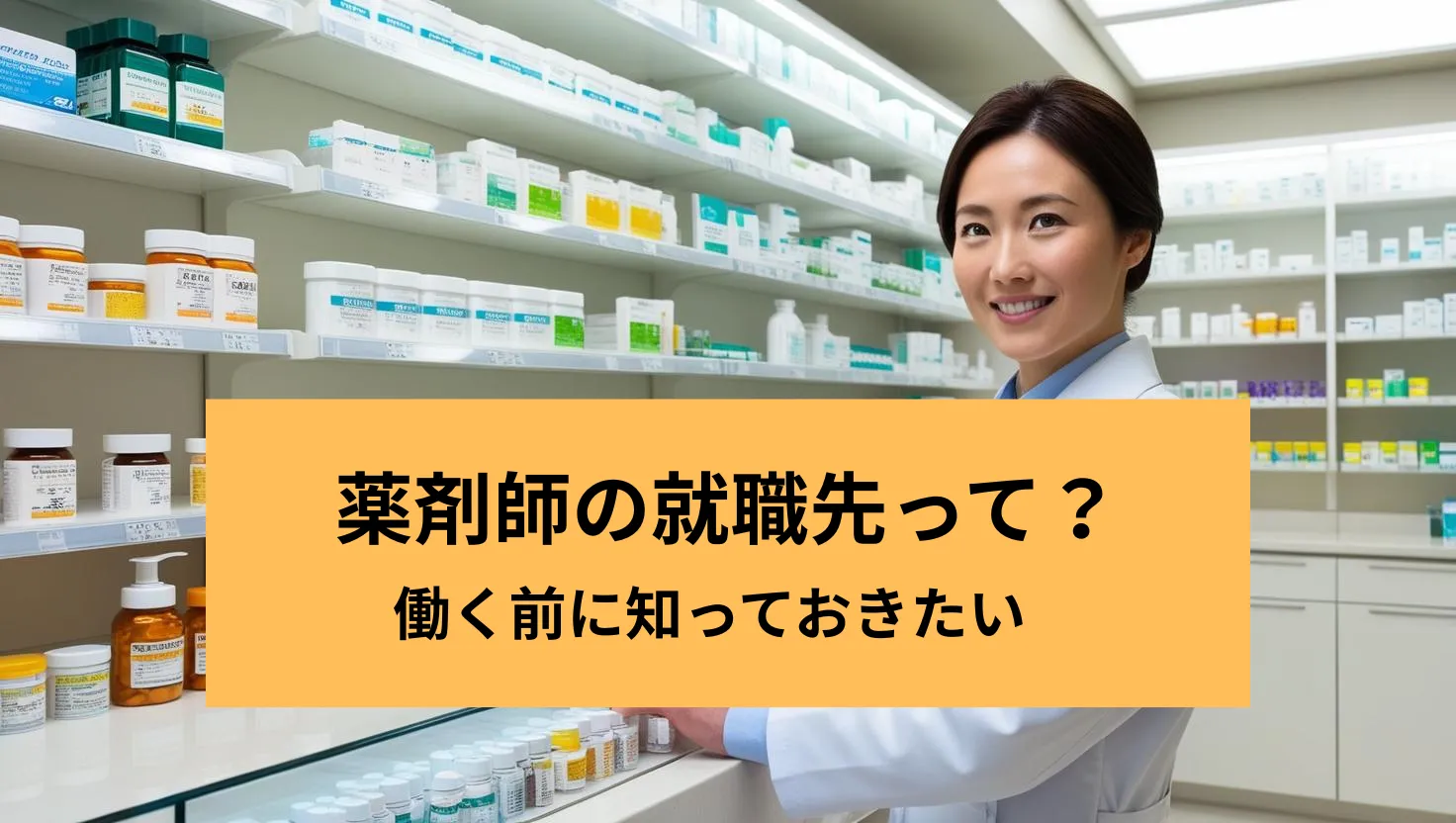


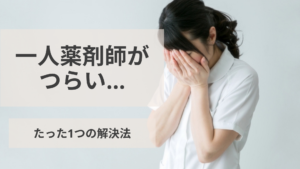

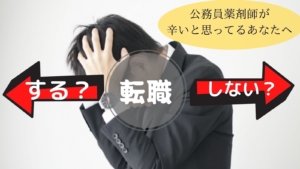
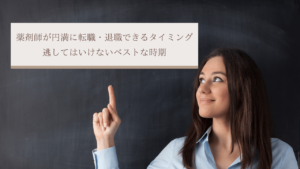
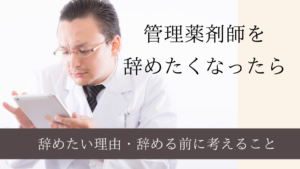

コメント